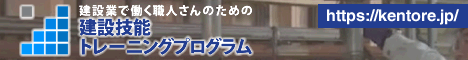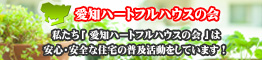住宅政策の変遷 面積から性能へ 省エネ基準義務化は通過点
住宅政策の変遷 面積から性能へ 省エネ基準義務化は通過点
50周年記念特集号(第一弾) 国土交通省住宅局 石坂聡局長
――50周年インタビューにご対応いただきありがとうございます。弊社50周年に合わせ、石坂局長にはこれまでの住宅政策について振り返っていただければと思います。
石坂局長:50周年おめでとうございます。日本の住宅政策は戦後の住宅不足から始まり、昭和43(1968)年に全国の住宅総数が世帯数を上回る逆転現象が起こりました。さらに日本住宅新聞社が創業した昭和49(1969)年の前年には、全都道府県レベルで住宅総数が世帯総数を上回りました。今でこそ空き家が800万戸ありますが、当時は現在と真逆で、日本の住宅難を解消しようと取り組んでいた時代です。また都心では人口増加に対応すべく、ニュータウンの開発も行われました。このように住宅政策からみて、まさに激動の時代にスタートされたんだなと思った次第です。
それでも日本の住宅は、数が充足した後に「数から質へ」という段階に移りました。この「質」というのは、今の住宅の性能とは違い、2000年ごろまでは主に面積のことを指していました。「日本の住宅はウサギ小屋」と言われた時代もありましたが、例えば、昭和46(1971)年に作った「第2期住宅建設5箇年計画」では、「昭和50年度までに全ての世帯が、小世帯は9畳以上、一般世帯は12畳以上の規模を有す」と面積について目標を掲げています。以降、昭和51(1976)年にスタートした第3期の5カ年計画では「最低居住水準」と「平均居住水準」の中で、バブル経済の様相を帯びてきた昭和61(1986)年の「第5期住宅建設5箇年計画」では「誘導居住水準」という基準の中で住宅規模についての目標が設けられております。
このように広さを求めてきた住宅政策ですが、最近は単身世帯を始め、核家族、結婚されない方の増加など、「家族の形」も変化しつつあるように感じます。例えばマンションでは比較的コンパクトな住まいを志向される方が増えていて、「駅が近い、利便性がある物件」の需要が増えています。また、若い方のライフスタイルも、物を持つことを重視しない形に変化してきました。昔は結婚すると、大きな婚礼家具を新居に持ち込んでいましたが、それこそ車も「カーシェアでいい」という考えが支持されている時代です。このように生活そのものが変わってきていている中、家の広さはどうあるべきなのか。
これは持ち家だけではなくて賃貸にも当てはまりますが、どちらかというと我々はファミリー向けを追い求めてきた歴史があります。実際、URをみると、郊外に広いファミリー向けの物件を大量に抱えています。でも、これから増えるのは単身の高齢者。広い物件は賃料が高くなり、ミスマッチが生じてしまいます。
例えば「住宅セーフティネット法」という既存の賃貸や空き家等の有効活用を通じて、「住宅確保要配慮者」が入居しやすい賃貸の供給促進を図ることを目的とした法律があります。今回、同法の改正を行い、大家さんが賃貸住宅を提供しやすく、要配慮者の方が円滑に入居できる市場環境の整備を行いました。ただ、住宅の登録基準については住戸の床面積が原則25㎡以上という要件が設けられているため、小さな物件が登録できません。一方で学生さんや社会人の若い方向けに大量に供給されてきたワンルームのマンションやアパートが存在しています。こうした物件の方が賃料も面積もお手頃で、単身の高齢者の方も入居しやすいと思うんですよね。学生さんが減っているわけですから、大家さんも幸せになります。それなのに「25㎡以上必要だ」という要件が邪魔をする。もうね、アホかと(笑)。すみません、平成29年に施行した住宅セーフティネット法ですが、当時の担当課長が私でした(笑)。
そういう形で考えると、我々役所の方も、とにかくファミリー向けを意識してやってきた。しかし、世代の実情が変わってくる中でマインドをまず変えなきゃいけないのかなと思いますし、前述のことも含めた上で、この際、面積を基準にするべきなのかどうか、そこからまず考えなければいけないなと考えています。
――この50年間で住宅業界には様々な動きがあったと思います。大きいトピックをいくつか挙げてください。
石坂局長:耐震の問題が挙げられます。 昔の教科書では震度7について、「30%以上の家が倒壊します」、震度6で「30%以下の家が倒壊します」と書いてありました。つまり 震度6や7が来れば、「家が倒壊するのが当たり前」だった。新耐震基準ができた昭和56年、私は中学生でしたが、当時はまだ家は壊れるものだと思っていましたね。
その上で、やはり阪神淡路大震災は大きな転換点でした。実は私の最初の赴任地が神戸。あのような被害があって初めて地震の悲惨さを実感しました。そこから様々な耐震改修促進法ができ、いろんな支援制度も少しずつ充実させてきたのかなと思います。実際、阪神淡路大震災の頃の全国の耐震化率は65パーセントぐらいで、つまり3軒に1軒は耐震性能がなかった。それが今では地域的な偏在はあるにしても、全国ベースで見ると大体9割ぐらいまで耐震化率は上がってきています。
それから、住宅性能表示制度がスタートしたのが平成12年(2000年)です。同制度はすごく大きなターニングポイントで、私は住宅政策からすると1番大きな転換点ではないかなと思っています。先ほども触れたように、それまで「住まいの性能」といえば面積一辺倒だったわけですが、この他にも省エネ、耐久性、バリアフリー、後にはピッキングやサムターンといった犯罪に対応する防犯性能も制度内に盛り込みました。そういった性能の視点があるということを知らしめるきっかけになったことは本当に大きいと思っています。個人的には2000年前後を境に、戸建て住宅の質は本当に変わったなと感じています。
その中で省エネ性能ですが、最近の家はもう本当によくできていて、それこそ省エネ基準どころじゃなくて、ZEHレベルの断熱性能が当たり前になってきた。ZEHレベルを有する新築住宅の取得を支援する「こどもエコすまい支援事業」、「子育てエコホーム支援事業」を設けたこともあり、現在は9000の住宅事業者がZEHに参画していらっしゃる。昔はZEHというと、大手のハウスメーカーや一部の先進的な工務店だけが熱心に取り組んでいた印象でしたが、今、普通の工務店でも建てられるようになった。すごく大きな変化ですよね。だから来年の省エネ基準の適合義務化はもうただの通過点で全く心配していません。むしろ一気に次のZEH水準が当たり前になるような状況まで、基準を持っていけるんじゃないかな。もう次のZEH水準の規制に入りますかね(笑)。本当にできるんじゃないかと思うぐらいですよ。
この他、最近の若い方は「断熱ネイティブ」だといえます。暖かい家が当たり前ですから、省エネ基準レベルの性能がない住宅には住めないのではないでしょうか。空き家が増え、既存住宅が流通していないことが課題となっていますが、そうは言っても寒くて古い家には需要がないし、リフォームにも限界があります。「空き家が増えているんだから新築をつくらず、リフォームすればいいじゃないか」という意見もありますが、「実際問題、この家に住めますか」という疑問はでてくる。だから大工さんには省エネ基準やその先のZEH水準の義務化については「基準だからやる」というのではなくて、むしろ「やらなければ売れない」という認識で、お客様の需要に合ったものを建てていただければと思います。もちろん、既存のリフォームは重要です。現在、環境省さん、経産省さんで連携して実施されている「窓リノベ」などの施策もあり、大変好評です。住まいの断熱改修を部分的にやるだけでも効果が得られますから、こうしたものを利用して、既存の改修も進めていただければと思います。
日本住宅新聞提供記事(2024年6月15日号)
詳しくは、NJS日本住宅新聞社ホームページにてご確認下さい。
http://www.jyutaku-news.co.jp