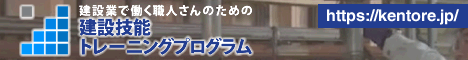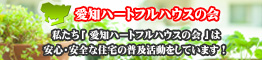大工・工務店がいなくなったらどうする?!
工務店不滅論
地域に根差した地場工務店は絶対に必要だ。地域住民の安全と安心のために、さらに地域社会を豊かにするためにも、なくてはならない存在である。それなのに、なぜか地域工務店に元気がなく消えていく。方向が見えないからだ。土壌が悪く、根っこが弱いからだ。
木造住宅がある限り、地域に根差した工務店は絶対になくしてはならないという視点で今回から数回にわたって地域に根差す、地場工務店不滅論を探ってみたい。
地域住民の命と財産を守る役割
NPO法人住まいの構造改革推進協会の鈴木芳郎理事が「東海耐震マイスター倶楽部」設立総会の基調講演で地域に根差す工務店の役割と題して次のように語り注目された。前段で、阪神・淡路大震災の被害地の中心であった神戸市長田地区で工務店を営んでいた社長の話に触れた後のこと―。
「木造住宅は、木材を切断することによって人の命を助けることも奪うこともできる。木造の構造をしっかり理解していれば、どこを切断したら助けることが出来るか瞬時に判断する事が出来る。地震発生後、十数分の間に多くの命を助けることが出来るのは、住宅の構造を理解し、道具がそろっている工務店であり、その工務店が救助のリーダーになることである。(略)、工務店は住まいを作るだけでなく、地域に根差し、地域住民の命を守るために、与えられた社会的役割と存在価値を認識し、日ごろの情報収集と知識力・技術力・判断力に磨きをかけて欲しい」
これは同様に大手ハウスメーカーにも言ってほしい所だが、設立総会では工務店対象であったことから「工務店の役割」で終わってしまった。
鈴木理事が言うように正に地域に根差した工務店は、地域社会に根ざさなければならない理由があり、役割があるということである。
「金儲け」や「利益追及」「経営者欲望満足」のためにのみ、住宅事業を行ってはいけない、ということである。また日本は地震や台風・火災等の災害大国であるだけに、地域住民の命を守らなければならない役割があるということである。そういう意味で地域に消防団や町医者が必要なように、地場工務店も必要不可欠ま存在なのである。
これだけは「イザ、地震対策」「イザ、火事対策」という災害時災害復興のためだけの要員としてのみとられがちだが、当然その役割は大であり、そのために、絶対になくてはならない存在であるが、その他にも日頃の工務店経営の役割は大であるを忘れてはならない。
それは何か。
「災害に強い家づくりだけでなく、住宅貧乏から解放させ、豊かな住生活、幸せな家庭生活を生み出す工場となる家を作ること」。そして「日頃、地域住民が安心・安全に暮らせる街守り、家守りをする工務店力(一社で不可能なら数社またはグループで)をもたなければならない、ということである。
「子供が外で遊べない地域社会」
「年寄りの散歩もままならない地域社会」
「老人の孤独死が増えている」
こんな地域社会になってきているのはどうしてなのか。
それは「地域社会の安全・安心を守る地場工務店」が少なくなり、元気がなくなってきたからではないか。
また、住宅資材の工業化・新建材・ユニット化によって建築職人をゲンゾウ大工化させ、職人の希望をなくし、元気を奪ってきたからではないか。
このまま対応策に力を入れないと建築大工減少を止めることはできない。この減少を国を挙げて根本的に止める対策を打ち出さないかぎり住宅事業界だけでなく豊かな国づくりも望めそうもない。
住宅に関する人は、「家づくりは人づくり・国づくり」であることを強く認識して欲しいのである。
建築大工の減少著しい 30才未満が7万人以下に
それでは建築大工人口動向と工務店数の動向を見てみよう。

別表のとおり、建築大工も工務店数も確実に減少している。
物づくり工務店(商務店ではない)にとってなくてならない建築大工が平成17年の総務省調査によると53万9,868人と平成7年調査時に比べ22万1,954人(29%強)の減少。昭和60年に比べ26万5,921人(33%)もの減少となっている。年齢別で見るとさらに悪く

なっている。
20才以上が平成17年には、平成2年の3分の1以下の6,000人を切り、30才以下は10年前に比べ33%も減少、同時に高齢化が進み、平均年齢が48.7才と高くなってきている。
一方、工務店数はどうか。工務店の定義がないため工務店という調査項目はないが、総務省の統計分類では、木造建築工事業所と建築工事業所の一部が入るものと見られる。木造建築工事業は「主として木造建築物のみを完成する事業所をさす」としており寺社建築会社を除いて住宅建築請負の木造工務店と見て良い。それだけでも別表のとおり、平成18年調査では平成13年に比べて約9,000社(実質8,910事業所)も減少している。
「建築工事業について総務省の定義は「木造のみでなくRC・S造等の建築物を完成する事業所」となっており、木造以外にRC造・S造建築を中心にやっている事業所で、工務店と呼ばれる事業所も数%含まれているとみて良い。特に木造規制の強い沖縄や大都市圏の防災地域にいる工務店の多くは、木造もやるが非木造の請負が多い兼業の事業所である。この分野の事業所も別表のとおり大幅な減少を示している。
平成13年に比べ、5年後の平成18年には3,617事業所も減少。平成3年に比べれば8,476事業所も消えている。
工務店の定義はないものの、弊社の読者対象としている工務店の概念(都内や大阪市内の工務店の多くはRC,S造が多くなっているものも含め)の中には、木造中心ではあるが、地域性によってRC・S造も建築に取り組まなければならない建築業者も入ってくるため「工務店数」という場合、この「建築工事業所」の中から、約10%位は「工務店」の範疇に入れても良いではないか、と見ている。従って我が国の工務店数は、ざっと86,756事業所(83,676+8,080)となる。建築リフォーム事業所まで入れるともっと増える形になるが、いずれにしても、全体の傾向として、工務店の減少は年々、進んでいる事は間違いない。
この減少傾向の原因の一つに新築住宅着工数の減少に伴う過当受注競争があげられるが、「新築量が減少したから」「受注競争に負けたから」と言って「倒産しても仕方がなかった」という訳にはいかないのが住宅業界の特質なのだ。
また受注競争において「勝ち・負け」はあっても「住宅の質は、受注の勝ち負けだけで決めれない」という特質があるという事である。
それは「家には人をつくる」というパワーがあるからだ。
家づくりを軽く見てはいけない
命を担保にしてまで持つマイホーム=「住宅」。
工務店やハウスメーカーにとっていの一棟は何棟分の1か何百棟分の1か、大手ハウスメーカーになると何万棟分の1の価値しかないのが、お客にとっては、長期住宅ローンを組み生命保険をかけて求める「命がけそのもの」の一棟である。それだけに重く、大きな買い物であるだけに、受注競争(営業力)や営業テクニックで、住宅受注のを決めるのではなく「住まい手」とプロの「つくり手」が、同じ目線で住宅の持つ役割・目的・影響力等を考慮し、予算をにらみ協働で「幸せをもたらす工場」としての住宅をつくっていくべきではないだろうか。
次回は、大工・工務店の減少の背景に新設住宅着工量との関係もあるので、その点から論じてみたい。
工務店数もの大幅減 食い止めなければ大変
<日本住宅新聞H22.6.25記事抜粋>