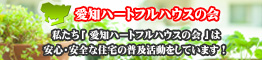「第42回 東京モーターショー2011」積水ハウス、住宅メーカーとして初の出展決定
「第42回 東京モーターショー2011」積水ハウス、住宅メーカーとして初の出展決定
~「グリーンファースト」から考える、EVとスマートハウスの新たな関係を提案~
積水ハウス株式会社は、平成23年12月2日(金)~12月11日(日)(一般公開は12月3日(土)から)まで東京ビッグサイトで開催される「第42回 東京モーターショー2011」(主催:一般社団法人日本自動車工業会)に、住宅メーカーとして初めて出展することを決定いたしました。
東京モーターショー2011では、"最先端の情報・環境・エネルギー技術が実現する人とクルマと都市の未来"をテーマとした「SMART MOBILITY CITY 2011」も開催される予定です。
積水ハウスはスマートハウスのリーディングカンパニーとして、先進のテクノロジーを駆使し、健康で快適に暮らしながら地球温暖化の防止にも貢献する環境配慮型住宅「グリーンファースト」を提案してきました。
今回の展示会では「グリーンファースト」から考えるEVとスマートハウスの関係を、ご紹介していく予定です。
■ 「グリーンファースト」について
「グリーンファースト」とは、安全・安心で高品質な住宅に太陽光発電や燃料電池を組み合わせて快適性・経済性を確保し、CO2や電力消費を大幅に削減できる環境配慮型住宅です。停電時の太陽光発電による非常用電源としての機能や、現在の節電社会において系統電力に依存しない太陽光発電や燃料電池などの「創エネ」性能が注目を集めています。
☆「グリーンファースト」の商品サイトは こちら をご覧ください。
<本件に関するお問合せ先>
積水ハウス株式会社
広報部
(大阪) 06-6440-3021
(東京) 03-5575-1740
※掲載内容は発表時点のものであり、現在の内容と異なる場合がありますのでご了承下さい。