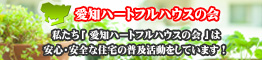HEMS関連機器を全国販売~ジャパン建材~
HEMS関連機器を全国販売~ジャパン建材~
今年の工務店の導入5000棟予定
ジャパン建材(東京都、大久保清社長)は1日から全国で、家庭用の電力消費を統合監視・制御するHEMS(ホームエネルギーマネージメントシステム)に関連する機器の販売を開始した。既に九州や東北、関東、首都圏第1・第2、中部、関西などの営業部ではHEMS関連機器の取り扱いを始めていいるが、同社JKサポートセンターが中心となって進めている販売体制が北海道と中四国の営業部でも整い、全国での販売開始となった。工務店によるHEMSの導入支援は今年5000棟を予定している。
詳しくは、日刊木材新聞紙面をご確認下さい。
(日刊木材新聞 H24.2.2号掲載記事抜粋)
日刊木材新聞ホームページ http://www.n-mokuzai.com/